治療ストレスの
緩和を心がけた
歯科治療
ほとんどの方にとって歯科医院は、痛い、怖い、行きたくないという場所ではないでしょうか。
苦手意識があると、我慢の限界が来て仕方なく来院という風になってしまいます。そうなると悪化が進み、残せる歯も残せなくなってしまいかねません。
当医院は、痛みを抑えて、気軽に行けるような医院を目指して診療しています。

一般歯科は
4段階の虫歯に
合わせた治療
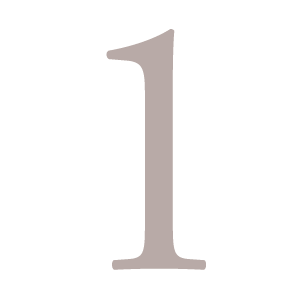
初期の虫歯(CO:シーオー)
歯の表面のエナメル質がわずかに溶け始めた状態で、見た目や痛みはほとんどありません。歯の表面が白く濁って見えることがあります。この段階では、フッ素塗布や丁寧な歯磨きで自然治癒を促すことが可能です。定期検診で早期発見し、進行を防ぐことが大切です。

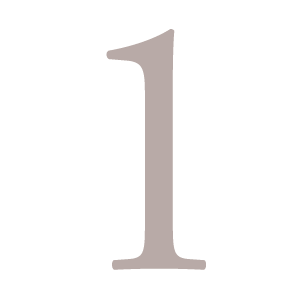
エナメル質の虫歯(C1:シーワン)
虫歯がエナメル質に小さな穴を開けた状態で、まだ象牙質には達していません。痛みはほとんどありませんが、冷たいものがしみることもあります。治療では、虫歯の部分を最小限に削り、歯科用プラスチック(レジン)を詰めます。早期治療で、比較的簡単に修復できます。

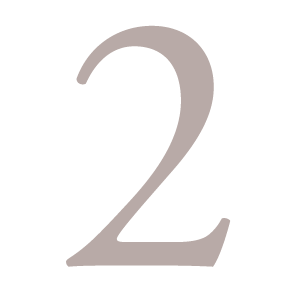
象牙質の虫歯(C2:シーツー)
虫歯が象牙質まで進行し、冷たいものや甘いものがしみたり、軽い痛みを感じることがあります。虫歯の部分は茶色や黒く変色していることがあります。治療では、虫歯を完全に削り、詰め物(レジンや金属)で修復します。虫歯の範囲が大きい場合は、型取りをして詰め物(インレー)を作製します。

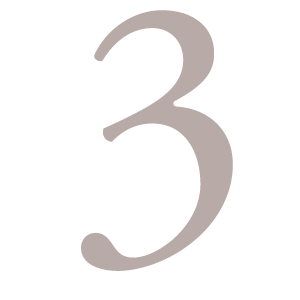
神経まで進行した虫歯(C3:シースリー)
虫歯が神経まで進行し、激しい痛みを感じることがあります。熱いものがしみたり、ズキズキと痛むこともあります。治療では、神経を取り除く根管治療が必要です。根管治療後、被せ物(クラウン)で歯を保護します。放置すると、さらに重篤な症状を引き起こす可能性があります。


歯の根まで進行した虫歯(C4:シーフォー)
歯の大部分が崩壊し、根の部分だけが残っている状態で、神経が死んで痛みを感じなくなることがあります。歯ぐきが腫れたり、膿が出ることがあります。多くの場合、抜歯が必要です。抜歯後、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで歯を補う必要があります。早期発見・早期治療が重要です。

ホワイトスポットの治療
ホワイトスポットとは初期の虫歯のこと
ホワイトスポットとは初期の虫歯のことで、主に歯の表面に白く濁った斑点状の変色ができ、特に痛みは感じません。普段からしっかりと歯が磨けていれば、初期の虫歯から進まないため、フッ素を塗布程度の処置で経過を見ることが多いです。ホワイトスポットの治療を行う場合は、変色した部分を削り、コンポジットレジンという歯科用プラスチックで局所的に詰めることになります。
ただ、コンポジットレジンは保険適用の一般的な材料ではあるのですが、普段の飲食での着色、咀嚼や歯磨きでの摩耗や脱離、プラークがつきやすくなるなどの経年劣化が起こるため、再治療が必要になります。どうしてもホワイトスポットが気になりケアしたい方には、定期的なホワイトニングをご提案する場合もございます。まずは日頃から虫歯予防を心がけ、ホワイトスポットが進行しないように丁寧な歯磨き習慣を継続しましょう。

乳歯の初期虫歯の治療
乳歯の場合は歯を磨く技術が未熟で口腔清掃が不十分なことが多い上、スクロースを含む食品(砂糖を多く含む甘い食べ物)の摂取機会が多いこと、永久歯に比べてエナメル質(歯の表側の組織)が薄く石灰化度(虫歯に対する強度や抵抗力)が低いため、う蝕(虫歯)への抵抗性が低く、進行が早いため進行度合いに合わせこまめに対応していくことが必要になります。

歯周病治療
歯周病の進行に合わせた
適切な処置が重要
特に自覚はなくても、少しの違和感程度に思っていたことが実は歯周病だったという事は少なくありません。歯を失う原因にもなる非常に心配な疾患です。早期治療を心掛けることはもちろんですが、体質によりかかりやすい口腔内の方もいらっしゃいますので治療後も油断せず、定期的な予防を行い再発を防止しましょう。
当院では特に歯周病の予防や初期段階の適切な処置に力を入れています。歯の歯石を除去するスケーリングや、PMTCなど保険外処置も行なっています。
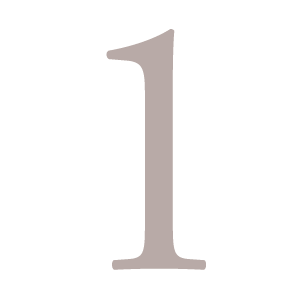
軽い歯肉炎
主な症状
歯ぐきが赤く腫れ、歯磨きやフロスで出血します。軽いむずがゆさを感じることもあります。この段階では、まだ歯を支える骨には影響が出ていません。
主な治療方法
歯科医院での歯石除去(スケーリング)と、正しい歯磨き指導が中心です。丁寧なプラークコントロールで、炎症を抑え、健康な歯ぐきを取り戻します。

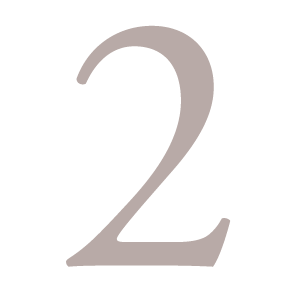
軽度歯周病
主な症状
歯ぐきの腫れと出血が続き、歯周ポケットが深くなります。歯を支える骨がわずかに溶け始め、口臭も出始めます。
主な治療方法
歯石除去(スケーリング・ルートプレーニング)で、歯周ポケット内の清掃を行います。必要に応じて、抗菌薬を使用し、炎症を抑えます。

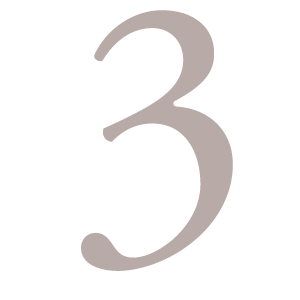
中度歯周病
主な症状
歯ぐきの腫れと出血がさらに悪化し、歯周ポケットが深くなります。歯槽骨の破壊が進み、歯がグラつき始め、歯ぐきが後退します。
主な治療方法
歯石除去に加え、歯周外科手術(フラップ手術など)や歯周組織再生療法(GTR法、エムドゲインなど)を行い、失われた骨や組織の再生を促します。


重度歯周病
主な症状
歯ぐきの腫れと出血がひどく、歯周ポケットが非常に深くなります。歯槽骨の破壊が著しく、歯が大きくグラつき、歯ぐきから膿が出て、強い口臭も出ます。
主な治療方法
歯周外科手術や歯周組織再生療法に加え、抜歯が必要になる場合もあります。抜歯後は、入れ歯、ブリッジ、インプラントなどの義歯で歯を補います。

歯周病治療では原因菌を減らす対策も重要
歯周病の原因はプラークバイオフィルム(歯垢)の中の細菌で、プラークは歯の表面や歯周ポケットの奥などに付着します。口腔内には500から600ほどの種類の細菌がおり、その中でも歯周病の原因菌とされるものは10から15種類程度です。
原因菌が増える元であるプラーク、そのプラークが歯や歯周ポケットに付着するリスクを高めるものは、歯石、う蝕、不適合な修復物(被せ物)、歯周ポケット、唾液の量、口呼吸などの悪習癖など様々あります。歯周病治療はさまざまな角度からのアプローチをし歯周病原菌を減らすことが必要です。

歯周病治療が終了するまでの来院回数の目安
歯周病治療にかかる来院回数は、歯周組織の状態、日頃のプラークコントロール(歯磨きの技術)、歯周病のリスクの高さなどにより異なります。健康な方の場合1〜2回のご来院で終了します。
歯周病のリスクの高さとは、歯肉からの出血の度合い、歯周ポケットの深さ(4ミリ以上で中度〜重度)、全身的・遺伝的な要素、喫煙の有無などを総合的に判断します。一般的には、治療後1年間は3カ月ごとの検診を行うことが望ましいですが、プラークコントロールの程度により検診回数が増減します。治療後もしばらくは厳重な管理が必要な場合、1ヶ月毎の定期検診を行うこともあります。

歯周ポケットが6ミリ以上の場合の歯周病治療
歯周ポケットの深さが6ミリ以上ある場合は重度の歯周病となります。
患者様自身でのプラークコントロール(日頃のブラッシング)や歯ぎしりなどの悪習癖の修正、歯科医院でのスケーリング(歯石を除去)や噛み合わせの調整、といった基本的な歯周病治療で改善しない場合、歯周外科治療を行います。歯周外科治療とは、歯茎や骨に対する外科的(手術を伴う)治療のことで、歯周組織(歯肉や粘膜)の再生や歯周ポケットの改善、審美性の回復を行います。
基本的な歯周病治療を行なっても、「歯周ポケットの深さが4ミリ以上ある」「プロービング(歯周ポケットの深さを測る検査)時に出血がある」「歯並びや歯の形などにより歯磨きが難しく歯周病が再発しやすい」などの場合は、歯周外科治療が必要になります。

歯肉退縮の治療について
歯周病は歯肉の炎症(歯肉炎)だけでなく、歯肉や歯槽骨、セメント質、歯根膜などの歯周組織が破壊される病気です。特に歯槽骨は破壊されると元には戻りません。
歯肉退縮は、歯の土台である歯槽骨が歯周病によって破壊されることで、歯肉にも影響し退縮が起こります。歯肉退縮は歯周病になっていなくても加齢とともに誰にでも起こるものではありますが、それを早めるのも遅めるのも普段のブラッシング、定期的な歯科医院での検診ができているかどうかです。歯周病治療によりそれ以上悪くならないよう現状維持することが最善ですので、違和感や異常を感じたらできるだけ早めのご相談をお勧めいたします。

歯が抜けた
場合の処置
TREAT.01
入れ歯治療
入れ歯治療には保険でできるものと自費治療になるものがあります。保険で認められた作製方法や材料はかなり限られたものになります。薄さ、精密さ、見た目の違和感の無さ、耐久性を求めた場合、保険が効かない自費での製法や材料でないと実現できないという面があります。

TREAT.02
重い虫歯や歯周病で
歯を失った場合
重い虫歯や歯周病で歯を失った場合、感染源をしっかりと除去した上で、差し歯や部分入れ歯、ブリッジやインプラントといった治療方法が必要になります。自然な見た目に仕上がるように治療しようとした場合、保険治療では選択肢(審美性や強度面など)が限られるので、自費治療もご検討いただく事になります。

TREAT.03
少しの違和感、痛みのあるうちに
ご相談ください
痛みや違和感は歯のSOS信号です。SOSを無視して虫歯を進行させてしまうと痛みすら感じられないほどのダメージとなるおそれもあります。また痛みには波があります。しばらく痛みが引いたからと言って安心はできません。虫歯は自然に治癒することはありません。ひどくなって骨にまで影響が及ぶとインプラント治療さえ行うことが困難になります。痛みや違和感を放置せず、できるだけ早期に治療を行うようにしなければなりません。

一般診療・歯周病治療の注意点
歯の仮蓋をしている場合
歯の仮蓋(かりぶた)とは、歯の治療中に歯を一時的に保護するために使用されるカバーのことで、仮封(かふう)や仮詰め(かりづめ)と呼ぶ場合もあります。
歯の仮蓋の目的
- 唾液や食べかすが詰まって細菌感染するのを防ぐ
- 根管治療で使う消毒薬の効果を持続させる
- 根管の中を無菌状態に保つ
- 特に前歯の場合、治療中の見た目を良くする
- 削った歯を保護する
- 噛み合わせの高さを維持する
仮蓋を付けている間は、ガムやもちのような粘着性のある食べ物や硬いものは噛まないようにするといった点にご注意ください。もし外れてしまった場合は、仮蓋を紛失しないようティッシュなどの柔らかいもので包み保管し、できるだけ早く再仮封するために、歯科医院へご連絡ください。

詰め物や被せ物が外れてしまった場合
まずはお電話にてご連絡ください。急患対応の有無など次回のご予約をお取りいたします。
当院が休診日の場合は、診療日までお待ちいただくか、日曜・祝日でも診療されている歯科医院で応急処置をお受けください。
また、詰め物・被せ物が外れた場合は以下の点にご注意ください。
- 外れたものはティッシュのような柔らかいもので包むかケースに入れて保管
- 自分で接着剤でつけない
- 硬いものは食べない(負担かかるため)
- 冷熱刺激のあるもの飲食は避ける(痛みが出る可能性があるため)


